ようこそ!Nurse Magazineへ。
こんにちは、ナスマガのYUKIです。
人工心肺
人工心肺とはなんでしょうか?
そこから掘り下げていきましょう!!
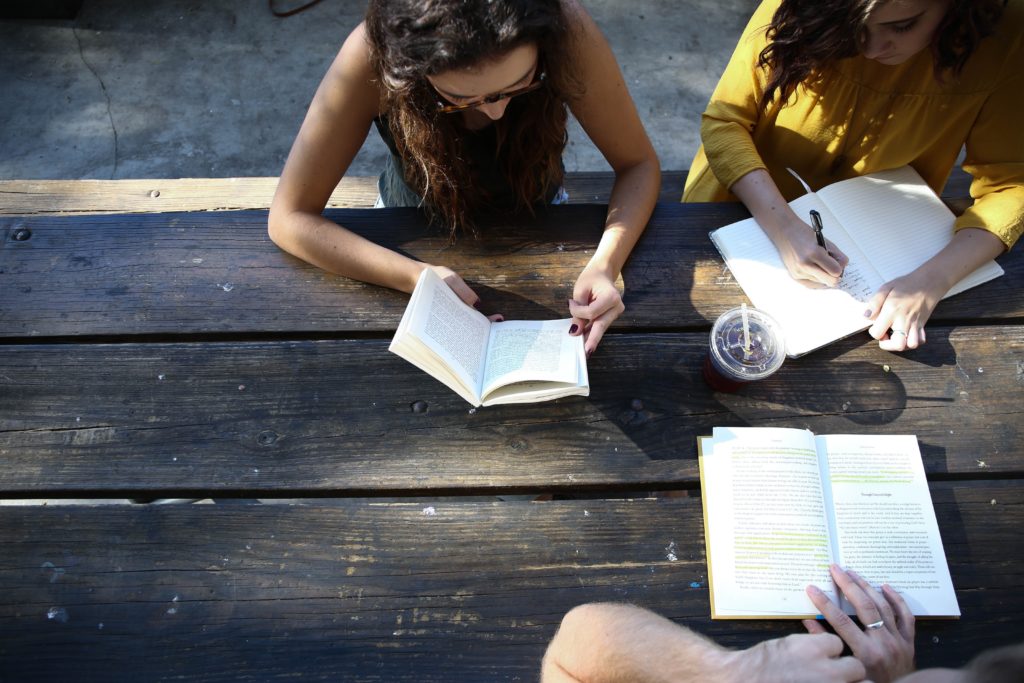
人工心肺とは?
さて、看護学生の皆さん。
心臓の手術ってどうやって行っているか知っていますか?
僕は学生の時は知りませんでした。
1回生の時とか、遊んでバイトしかしてませんでしたからね笑。
実際は胸を切開して心臓を直接手術しているんですが。
普通に考えて、動いている心臓を手術するって、すごく高度な事だと思いませんか?
それを可能にしているのが、人工心肺です。
人工心肺を使用する事で、一度心臓の動きを止めて心臓の手術をすることができます。
※オフポンプと言って、心臓を止めなくて手術を行う方法もありますが、それはまた今度の記事で…
これは国家試験でも必修の範囲レベルの内容ですが。
心臓の血液を運ぶ流れはご存知ですか?
上大静脈・下大静脈へ全身からもどってきた血液は、右心房→右心室→肺動脈→肺(ここで酸素を受け取る)→左心房→左心室→大動脈(アオルタ)→全身へ→はじめに戻る。
この流れになります。
心臓を止めてしまうとこの流れを止めてしまいます。
これを代用してくれるのが人工心肺です。
仕組みとは
それでは仕組みについて、説明していきましょう!
ここで重要なのは”脱血管”と”送血管”です。
心臓の代用をする為には、体から血液を回収・血液を体に送ることが必要です。
それを可能にしているのが、脱血管と送血管。
まず、脱血管を上大静脈・下大動脈の2箇所に挿入。
そして、送血管を大動脈に挿入します。
こうすることで、全身から、血液を回収し体外の機械(遠心ポンプ)で酸素化し、大動脈から全身へ送り出します。
遠心ポンプは、遠心力を利用して全身から血液を回収、取り付けられた人工肺で酸素化し、全身へ送ります。
人工心肺使用中は大動脈を遮断し、完全に人工心肺のみの循環へ移行します。
大動脈を遮断すると、心臓の冠動脈への血流が完全に停止し、虚血状態に陥ります。
心筋は虚血状態になると、約30分で不可逆的な障害を受けると言われています。
そこで、心筋へのダメージを抑える為に、心筋保護液を冠動脈から注入し心臓の代謝を抑えます。
副作用は?
人工心肺の影響は複数存在します。
- 炎症反応
- 凝固系の影響
- 低体温
- 血液希釈
- 物理刺激
以上が存在します。
炎症反応
人の体は異物と接触すると、炎症反応を示す性質があります。静脈ラインやバルーンカテーテルなどが挿入されている時に、発熱を来すことがありますよね?それと同様の作用になります。
人工心肺についても同様の事が言えます。
炎症反応が大きくなることで、好中球エラスターゼと呼ばれる炎症物質が増加します。
そして、この好中球エラスターゼは人工心肺離脱後に肺障害を引き起こす事があります。
ICUへ入室後に呼吸器系の異常が引き起こされた場合は、その影響が高いです。
凝固系への影響
血液は自分の体の中で循環している時は、凝固(固まること)していませんが、一度体の外へでると凝固する性質があります。
かさぶたもこれですね。
人工心肺も例外ではなく、脱血管より回収した血液は前述した通り凝固してしますのです。
人工心肺の回路内や人工肺内で凝固してしまうと、人工心肺が回らず作動させる事ができません。
そこで、使用するのが”ヘパリン”という薬剤になります。
ヘパリンには血液が凝固しにくくなる効果があり、手術中に使用します。
ACTという数値があり、一般的に400秒以上とし管理します。
ACTとは、活性化全血凝固時間のことを言い、フィブリンが形成されるまでの時間を表した数値です。
いわゆる、血液が固まるまでの時間と言ったところでしょうか。
正常値は90〜130秒
よって、人工心肺での400秒とは固まりにくくしているということです。
ICU看護師の役割を説明すると、患者さんがICUへ入室した直後にACTを測定します。
医師はそのACTを参照し、”プロタミン”投与の指示を出します。
プロタミンとは、ヘパリンと拮抗作用のある薬剤でACTを正常値へ戻す効果があります。
看護師は医師の指示の下、プロタミンを投与。
そこで、需要なのはドレーンが閉塞しないか?です
ACTが短縮される事で、出血リスクを回避できまずが、反面血液が固まりやすくなった為、ドレーンの閉塞に注意し、過度の排液量低下を観察してください。
低体温
手術中は心臓へのダメージを最小限に抑える事が必要になります。
そこで、手術中は低体温で管理することで代謝を抑え、酸素消費量を最小限に管理します。
しかし、低体温で管理することで様々な影響が引き起こされるので、以前書いた”低体温療法”の記事も参考にしてみてください。
血液希釈
低体温での管理を必要とする為、必然的に生体の抹消血管抵抗は高くなります。
抹消の血管が細くなり、血液が行き渡りにくくなります。
それを改善させる為に、血液希釈を行いリンゲル液を中心に1500〜2000mlの輸液を負荷します。
血液希釈することにより、血液の粘稠性を下げ(血液をサラサラ)、通りやすくします。
ここで、覚えておきたいことは、輸液を過度に負荷することで血管内の浸透圧が低下し、間質へ水分が逃げてしまうということ。
術後、手術室看護師から術中の水分バランスが申し送りされますが、その際概ね+バランスで手術が終了します。
その余分な水分は術後数日してから、間質から血管内へ戻ってくるため、術後適切に利尿を行う必要がある為、注意が必要です。
現場ではよくサードスペースから水が戻ってくる。
と会話があります。
このサードスペースとは間質のことです。
物理刺激
最後に物理刺激について。
人工心肺の回路には、ローラポンプという器具が取り付けられています。
遠心ポンプに加え、ローラーポンプにより回路内へ血液を回収しています。
このローラーポンプによる物理的な血液の刺激は、血液内の赤血球を破壊してしまいます。
赤血球が破壊されることで、酸素運搬能が低下し、貧血を呈する為術中にRBCを輸血することはしばしばです。
赤血球が破壊されると、赤血球ないのヘモグロビンが遊離され、体内を循環し腎動脈を閉塞させ、腎不全を引き起こすリスクもあります。
術後の尿量や腎機能データに注意が必要です。
今日は人工心肺の概要についてでした。
受け持ちの際は医師へ確認の上、看護していってください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
こちらにおすすめの転職サイト載せた過去記事があるので、見てみてください。







コメント